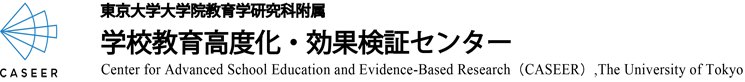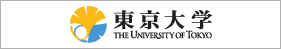運営委員
センター長
本田 由紀(ほんだ・ゆき)

比較教育社会学コース・教授
主に,家族と教育,教育と仕事,仕事と家族という,異なる社会領域間の関係について調査研究をしています。90年代以降の日本社会では,この3つの関係には矛盾が露わになっています。たとえば家庭教育に対する圧力や格差の高まり,「学校から職業への移行」の機能不全,仕事の不安定化による家族形成の困難化などです。それらをどう立て直していくか,行政や草の根的な運動がいかに関わってゆくべきかを考えています。
副センター長
額賀 美紗子 (ぬかが・みさこ)

比較教育社会学コース・教授
グローバル化の進展が家族,学校,子どものアイデンティティや能力形成に及ぼす影響に関心があります。国際移動する子どもに注目し,在米日本人家族や在日外国人家族のエスノグラフィー研究を行ってきました。学校の日常や家族の教育戦略の中でジェンダー,エスニシティ,階層,学力が交錯する過程を見ています。日米の学校調査を通じて多文化教育や市民性教育の国際比較も行っており,マイノリティを包摂する教育と社会のありかたを研究中です。
<主要著書>
- 『新グローバル時代に挑む日本の教育-多文化社会を考える比較教育学の視座』(共編著)2021年
- 『日本社会の移民第二世代-エスニシティ間比較でとらえる「ニューカマー」の子どもたちの今』(共著)2021年
- 『移民から教育を考える―子どもたちをとりまくグローバル時代の課題』(共編著)2019年
- 『越境する日本人家族と教育 ―「グローバル型能力」育成の葛藤』2013年
北村 友人 (きたむら・ゆうと)

学校教育高度化専攻・教育内容開発コース・教授
グローバル化時代における教育のあり方について、政治・経済・社会などとの関わりのなかから理論的および実証的に明らかにすることを目指しています。そのために、アジアの途上国を中心とした学校教育の充実に関する研究、日本の学校での「持続可能な開発のための教育(ESD)」概念にもとづく安全教育の可能性に関する研究、高等教育の国際化と国際協力に関する研究などに取り組んでいます。これらの研究を通して、教育の公共性とは何であるのか、深く考えていきたいと思っています。
<主要著書>
- Emerging International Dimensions in East Asian Higher Education, Springer, 2014年(共編著)
- The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia, Springer, 2009年(共編著)
- 『激動するアジアの大学改革』上智大学出版、2012年(共編著)
- 『揺れる世界の学力マップ』明石書店、2009年(共編著)
山本 義春(やまもと・よしはる)

身体教育学コース・教授
生体情報や健康関連情報のデータ分析が専門です。研究面では、教育や医療のフィールドを念頭に、データを如何に取得するか、どのように分析するか、結果を如何に解釈するか、健康リスクの評価や予防介入にどのように活かすか、といった問題について、生理測定、信号処理、モデリング、統計解析などの立場から考究しています。扱うデータは、標準的な生理測定データに加え、行動・社会医学的情報まで多岐にわたります。教育面でも、多様な興味関心を持つ学生や研究者に、情報化社会に相応しい専門的かつ総合的な「分析力」を身につけてもらうことを目指しています。
WEBサイト
福留 東土 (ふくどめ・ひでと)

大学経営・政策コース・教授
本センターは、学校教育を主な対象とし、教育による人間の成長・発達や教育を巡る諸現象について幅広くアプローチしています。現在のセンターの活動は、研究と実践の架橋、教育・学習の効果検証、グローバル化の中での教育のあり方といったテーマが中心ですが、これら以外にも様々なテーマを対象に活動を行っています。専任教員や運営委員の専門領域は多彩ですし、研究科の教員・学生、附属中等教育学校関係者、多様な立場の教育の研究者・実践者など、幅広い人々の関与と協力によってセンターの活動が成り立っています。本センターをひとつのハブとしながら、多くの人々が教育に関心を寄せ、考え、議論できるような場でありたいと思います。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
私の専門は高等教育論(比較大学論、大学史研究)です。主にアメリカの大学を対象に、比較および歴史の手法を用いて研究を行っています。アメリカの大学は日本の改革のモデルであるとみなされていますが、私はそれよりも大学のあり方について思考するための題材としてアメリカの大学を位置付けています。歴史的にアメリカの大学では、教育、研究、管理運営、社会サービスなどについて、様々なアイディアが提起され、様々な取組が行われてきました。大学について思考する上で魅力的な知識の宝庫であるといえます。それを通して大学一般のあり方を考えると同時に、日本の大学について考えを深めることが大切であると考えています。
<主要著書>
- 『カリフォルニア大学バークレー校の経営と教育』(編著、2019年、広島大学高等教育研究開発センター高等教育研究叢書149)
- 『専門職教育の国際比較研究』(編著、2018年、広島大学高等教育研究開発センター高等教育研究叢書141)
- 『大学マネジメント論』(分担執筆、2020年、放送大学教育振興会)
- 『大学経営・政策入門』(分担執筆、2018年、東信堂)
栗田 佳代子(くりた・かよこ)

学校教育高度化・効果検証センター 教授
大学総合教育研究センター(兼任)
高等教育における教員の資質向上に寄与するための質の高いFDプログラムの開発と普及支援を研究しています。本学においては大学院生および教職員を対象とした「東京大学フューチャーファカルティプログラム」を担当し、その実践を行いつつ大学教員準備プログラムの発展可能性や人材育成を模索しています。また、大学教員自身の資質向上の一要素として「リフレクション」に注目しており、ティーチング・ポートフォリオおよびアカデミック・ポートフォリオの作成プロセスにおけるリフレクションの効果や、その普及支援に関する研究に取り組んでいます。
個人ページ https://kayokokurita.info/
<主要著書・論文>
- 栗田佳代子, 吉田塁, 大野智久 (2018) 「教師のための『なりたい教師』になれる本!」 学陽書房
- 栗田佳代子(監修)吉田塁, 堀内多恵(編)(2017)『博士になったらどう生きる?―78名が語るキャリアパス』 勉誠出版
- 栗田佳代子, 日本教育研究イノベーションセンター(編)(2017)『インタラクティブ・ティーチング アクティブ・ラーニングを促す授業づくり』 河合出版
- 栗田佳代子(訳) スーザン A. アンブローズ,マイケル W. ブリッジズ,ミケーレ ディピエトロ,マーシャ C. ロベット,マリー K. ノーマン(著) (2014)『大学における「学びの場」づくり よりよいティーチングのための7つの原理』玉川大学出版部,(Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C. and Norman, M. K. (2010) How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching. Jossey-Bass: San Francisco)
- Kurita, K. (2013) Structured strategy for implementation of the teaching portfolio concept in Japan, International Journal for Academic Development, International Journal for Academic Development, 18(1), 74-88 (DOI :10.1080/1360144X.2011.625622)
片山 勝茂 (かたやま・かつしげ)

基礎教育学コース・准教授
対立する複数の価値観が並存しながらも、自由で平等な市民が協力して維持する、正義に適った安定した民主的社会はいかにして可能か。ジョン・ロールズが残したこの問いに教育学の立場からアプローチするべく、「教育と人間と社会のあり方」を考察しています。特に関心を持っている教育のフィールドは、多文化社会イギリスと日本におけるシティズンシップ(市民性)教育と道徳教育です。
<主要著書>
- Education and Practice: Upholding the Integrity of Teaching and Learning(Blackwell Publishing)(分担執筆)
- 『道徳教育の可能性――その理論と実践』(ナカニシヤ出版)(分担執筆)
- 『英国の教育』(東信堂)(分担執筆)
岡田 謙介 (おかだ・けんすけ)

教育心理学コース・准教授
心理・教育・行動データをモデリングし,現象の理解と予測に役立てることに関心を持っており,そのためにとくにベイズ統計学の方法論と応用を研究しています。心や行動について科学的に理解していくためにも,社会科学的な問題を実証的に解決していくためにも,統計学の理論と方法を役立てることのできるフィールドは私たちの未来に広がっていると思います。
宇佐美 慧(うさみ さとし)

教育心理学コース・准教授
教育学・心理学・疫学・医学を主軸とした,行動科学における多変量データ分析の統計学的方法論と応用・実践に関心があります。特に,複数時点に跨る測定を通して得られる縦断データを利活用した変化のモデリング・統計学的因果推論・分類に関するテーマ,および入学試験・資格試験や心理検査・医学検査を中心としたテストに対する測定論的視座に基づく評価・設計やデータの測定・分析法に関するテーマについて,分野横断的な展開を目指して研究を進めています。
専任教員
岩渕 和祥(いわぶち・かずあき)

学校教育高度化・効果検証センター 教育高度化部門 専任助教
教育システムの国際化・グローバル化がどのようなメカニズムで起きるのかを研究しています。国際化・グローバル化は、経済的動機に基づいた「グローバル人材」の育成や人口減少への対処、地域創成とさまざまなアジェンダを内包しうるものです。だからこそ、そこにはアクター間での政治が発生しやすいといえます。中央のレベルでは、文部科学省と政治家、自治体のレベルでは、教育委員会と知事といった異なるアクターが、どのような国際化・グローバル化を志向し、また、それはどのような教育観に基づいているのか、そして最終的にそれがどのような改革として実行されるのかを明らかにすることを目指しております。
業績などの詳細は、こちら(https://researchmap.jp/kaz_iwabuchi)をご参照ください。
<著書・論文>
- 岩渕 和祥(2023)「日本の中等教育の国際化をめぐる政策過程に関するアクターレベルでの分析 −学習指導要領の改訂プロセスに着目して−」『国際学報』1, 1-18.
- Takahashi, F., & Iwabuchi, K. (2022). A Japanese University. In M. Byram & M. Stoicheva (Eds.), The experience of examining the PhD: An international comparative study of processes and standards of doctoral examination (pp. 120-133). Taylor & Francis.
- Iwabuchi, K. (2022). The government, market, and IB: An analysis of policy documents justifying the introduction of the IB. 国際バカロレア教育研究, 6, 125-141.
- Iwabuchi, K., Hodama, K., Onishi, Y., Miyazaki, S., Nakae, S., & Suzuki, K. H. (2022). Covid-19 and education on the frontlines in Japan: What caused learning disparities and how did the government and schools take initiative? In F. M. Reimers (Ed.), Primary and secondary education during Covid-19 (pp. 125-151). Springer.
特任教員
日高 一郎(ひだか・いちろう)
学校教育高度化・効果検証センター 効果検証部門 特任講師
上野 雄己(うえの・ゆうき)

学校教育高度化・効果検証センター 効果検証部門 中等教育ユニット 特任助教
精神的な落ち込みからの回復を促す心理的特性であるレジリエンスの構造や機能,発達に関して研究しています。対象は10代から90代の幅広い年代層の日本人やアスリートであり,大規模横断・縦断的な量的調査に基づき,探索的に検討しています。さらには,多様な現場や対象者に実施可能なレジリエンス増強のための簡易的なプログラムの開発・効果検証も実施しています。特に,個人差を重視し,環境・状況との相互作用から,健康やパフォーマンスなどのアウトカムに対する影響を多角的に捉えようと試みています。
〈主要論文〉
- 上野雄己・平野真理(2020). 個人と集団活動を通したレジリエンス・プログラムの再検証 教育心理学研究, 68, 322-331.
- Ueno, Y., Hirano, M., & Oshio. A. (2020). The development of resilience in Japanese adults: A two-wave latent change model. Health Psychology Open, 7, 1-7.
- 上野雄己・平野真理・小塩真司(2019). 日本人のレジリエンスにおける年齢変化の再検討――10代から90代を対象とした大規模横断調査―― パーソナリティ研究, 28, 91-94.
- 上野雄己・平野真理・小塩真司(2018). 日本人成人におけるレジリエンスと年齢の関連 心理学研究, 89, 514-519.
- 上野雄己・飯村周平・雨宮 怜・嘉瀬貴祥(2017). 困難な状況からの回復や成長に対するアプローチ――レジリエンス, 心的外傷後成長, マインドフルネスに着目して―― 心理学評論, 59, 397-414.
川村 真理(かわむら・まり)

学校教育高度化・効果検証センター 特任助教
アメリカと日本の高等教育における教育・研究人材養成ついて研究しています。主な研究テーマは、TA・RA、大学院講師をはじめとする教育系学生職員制度、学修・経済支援、高等教育無償化、奨学金制度等です。日本における学部から大学院までを通じた持続可能な奨学制度構築に寄与する制度設計に向けた研究や調査を行っています。
近年日本の科学研究力の低下が社会問題として取り上げられていますが、その要因の一つとして、研究職を目指す学生や博士課程進学者自体が減少していることがあげられます。アカデミアに優秀な人材を集め、教育・研究人材として育成するためには、従来通りの奨学制度や学修制度に捉われない柔軟な制度設計や学修方法の開発が不可欠です。研究を通じて、学生や教職員がその能力を充分に生かしながら、社会や大学の価値創造に貢献できる学修環境の実現を目指しています。
<主要論文>
- 川村真理(2019)「米州立大学の学生経済支援制度に関する比較的考察-政府補助減少期における授業料戦略と学生支援-」、『大学経営政策論集』第9号
- 川村真理(2020)「米国州立研究大学における大学院学生への経済支援」、『大学経営政策論集』第10号
- 林 隆之, 齊藤 貴浩, 水田 健輔, 米澤 彰純, 川村 真理, 安藤 二香(2020)「大学評価と運営費交付金配分の一体的改革の在り方」『大学支援フォーラム(PEAKS)評価WG調査研究報告』,SciRexセンターワーキングペーパー #4, 政策研究大学院大学
- 福留 東土, 長沢 誠, 川村 真理, 佐々木 直子, 蝶 慎一(2021)「COVID-19がアメリカの大学にもたらした影響―2020年上半期の報告―」、『東京大学大学院教育学研究科紀要』第60巻別冊
淺川 俊彦
学校教育高度化・効果検証センター 特任講師
横原知行
学校教育高度化・効果検証センター 特任研究員
柴山笑凜
学校教育高度化・効果検証センター 特任研究員
学術専門職員
金山 枝生(かなやま・えみ)

田村 琴栄(たむら・ことえ)
協力研究員
【学外】
佐藤真久 東京都市大学 環境学部 教授
白水始 国立教育政策研究所初等中等教育研究部 総括研究官
川本哲也 慶應義塾大学 文学部 助教
草彅佳奈子 名古屋大学 教育発達科学研究科 講師
齊藤萌木 聖心女子大学 現代教養学部 講師
発田志音 慶應義塾大学 湘南藤沢事務室 学術研究支援担当
松本祐香 株式会社ハマーズ NHK国際放送レポーター
劉靖 東北大学 大学院教育学研究科・教育学部 准教授
Dr. Wesley Teter UNESCO’s Asia-Pacific Regional Bureau for Education
【学内】
和泉潔 大学院工学系研究科システム創成学専攻システムデザイン学講座 教授
酒井邦嘉 大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系機能解析学講座 教授
佐藤香 社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター 教授
橋本英樹 大学院医学系研究科公共健康医学専攻疫学保健学講座 教授
藤田香織 大学院工学系研究科建築学専攻建築学講座 教授
山内祐平 大学院情報学環 学環長・教授