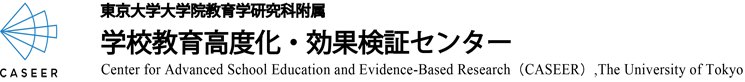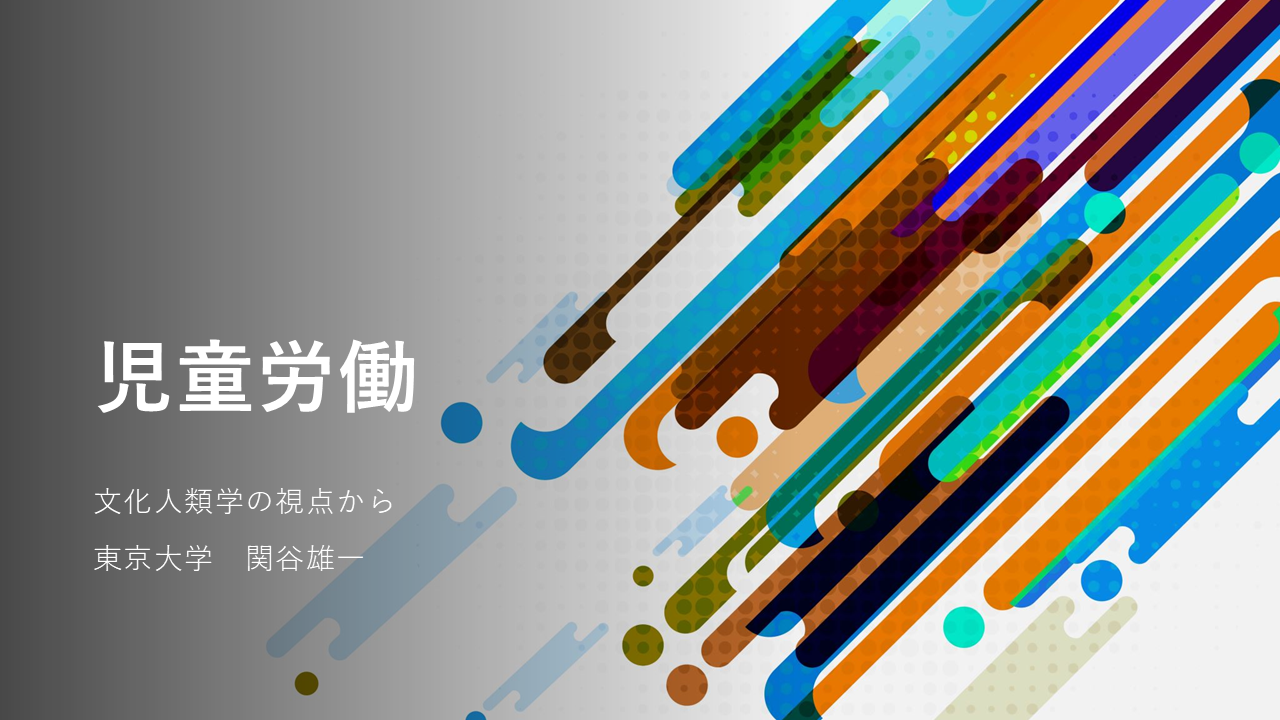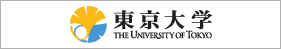東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「初等中等教育における探究学習への支援プロジェクト」において、児童生徒の発意や関心に基づく探究学習に対して専門の研究者が的確なアドバイスをすることにより、探究の成果をいっそう高度で充実したものとすることをねらいに、東京大学の教員もしくは大学院生がオンラインを通じて支援・指導を行っています。
今回は、埼玉県の中学2年生 Iさんの「児童労働について」の探究学習を通して出てきた疑問や悩みに、文化人類学研究室の関谷雄一先生がアドバイスしました。以下に、ダイジェストを紹介いたします。
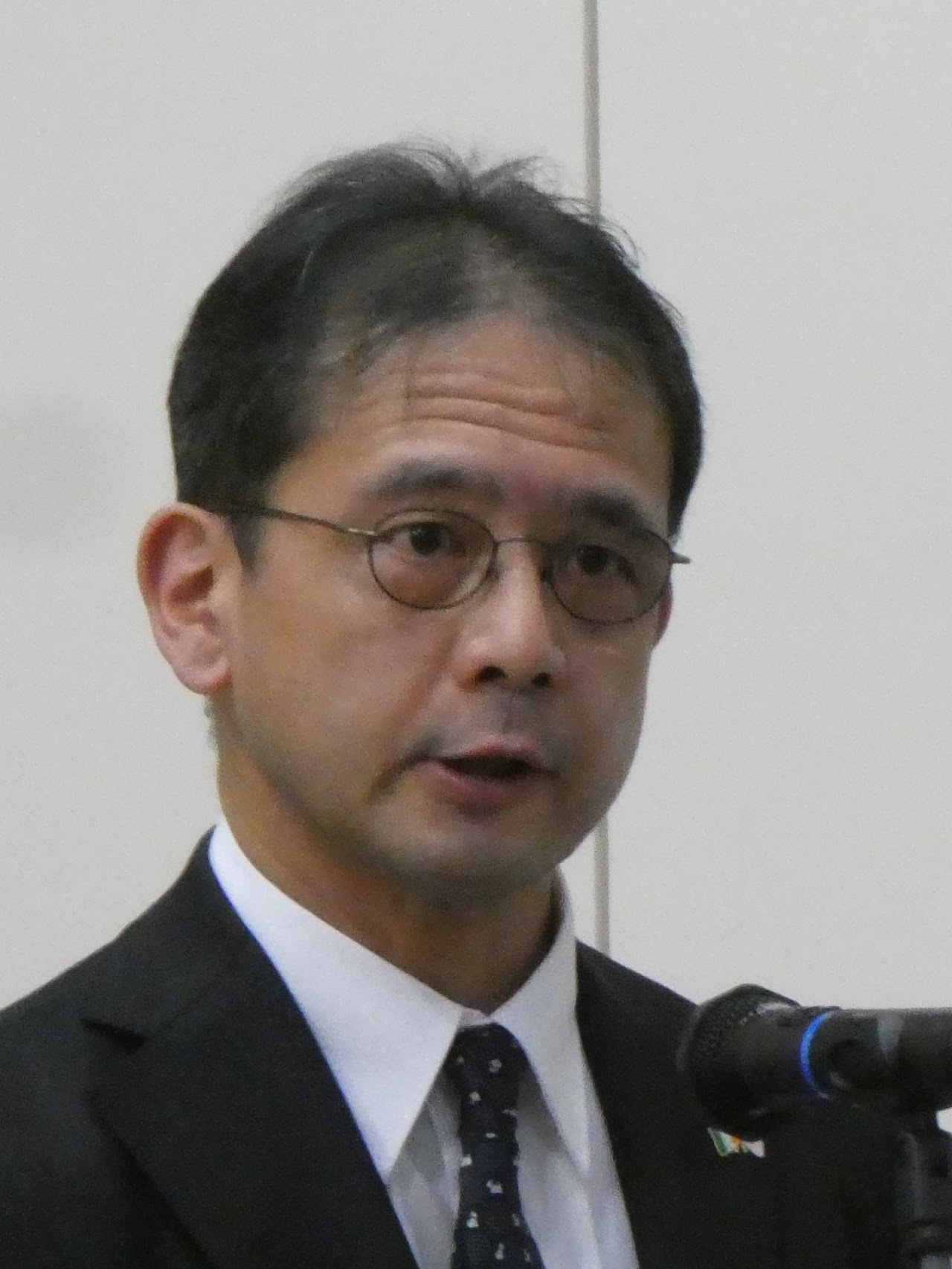 アドバイスした人:東京大学文化人類学研究室 関谷 雄一教授
アドバイスした人:東京大学文化人類学研究室 関谷 雄一教授
専門:開発人類学、応用人類学、農村・社会開発、震災復興、地域創生、人間の安全保障、アフリカ、日本
→ 関谷先生のページへ
Iさんのご相談
みんなが知っているかもしれないことでも、あなたがまとめて自分の言葉で周りの人に伝えることに意味がある
Series1. 児童労働について
Iさん:
私は学校の探究の時間で、児童労働をテーマに探究を進めています。私はこの探究で、働く子どもたちがいなくなる社会を実現するために、児童労働の事実を広め、児童労働を見て見ぬふりをする社会の風潮を変えるということを学習目標に設定しているので、今日は、実際に児童労働が行われているアフリカの地域など、その問題が起こっているところに行って活動している人の声などを聞かせていただきたいなと思っています。また、日本でも児童労働はあるのかについてもうかがいたいです。
関谷先生:
実は、事前に送っていただいた質問を拝見して、私の方でそれに答えられるような簡単な資料を用意したので、まずはそれをご覧いただきながらお話を進めていきたいと思いますが、よろしいですか?
Iさん:
はい、お願いします。ありがとうございます。
関谷先生:
私の専門は文化人類学なんですが、30年ぐらい前に、今はJICAボランティアという名前になっていますが、当時は青年海外協力隊という仕事で2年と6カ月、西アフリカのニジェール共和国というところに行って木を植えていたんですね。そこでは農村の子どもたちと一緒に遊んだり寝食を共にしたりしていたので、その時の思い出もちょっと含めて、このプレゼンを作っています。
→ 関谷先生からの「児童労働」についてのレクチャーを含む記事全文は、こちらからお読みいただけます。(PDFダウンロード)
Iさん:
(関谷先生のお話を受けて)本当に、その大人と子どもの境目がはっきりしていないっていうのは、調べていく中でもすごく思っていたことでした。
例えばその子が望んでいたら児童労働にならないのかとか、定義が難しいなってすごく感じました。
関谷先生:
そうですね。例えば徒弟制度についても、アフリカの子どもたちは、お年寄りに認められることや大人として扱われることをとても重要なことだと捉えていて、学校の先生に褒められることよりも、そういったことで自分の生き方に自信を持ったりする、そういうプロセスがあるんですね。
そういった、生きがいとして行う仕事のことをディーセントワークと言うんですが、私のかつての学生で、今は労働基準監督官になっている人の修士論文のテーマが、まさにその「子どものディーセントワークをどう考えるか」というものでした。その学生の出した結論は、子ども自身が生きがいだと感じられるような仕事であれば、やってもいいんじゃないか? というもので、私は素晴らしいと思って読んだんですけれども、これに対しては色々な見方があって、それはやっぱり子どもの人権を妨げるのではないかとか、先生方の間でも意見が割れました。それだけ難しい話なんです。
私自身も、アフリカの農村にいた時、恥ずかしながら自分のシャツなどを近くの川で子どもに洗ってもらっていたんですね。水汲みも村の女の子がやってくれていて、もちろんそれに対する対価は払っていたんですが、あれを児童労働だと言われると、ちょっとまずいなと思っていて。
要するに農村ではそれが自然になされているわけなんです。
農村の子どもたちにとっては、大人のために家事を手伝うことは、非常に自然なことで。でもそれがエスカレートしていくと、例えば親の代わりに町に働きに行かされる、などということになってしまう。だから、気をつけていないと子どもらしい生き方を奪われてしまうというのは、本当にそうなんです。
じゃあどうすればいいのかということなんですけれども、先ほどご紹介したILOとUNICEFの報告書の中では2つポイントが挙げられていて、1つは制度的な教育の徹底なんです。 やっぱり子どもはなるべく学校に通わせるということ。
学校に通っている時間は働けないわけですから、毎日真面目に学校に通ってもらって、一定の時間勉強をすることで、できれば高等教育につながるようなキャリアパスに進んでくれるというのが、望ましいということ。
もう1つは、社会の中で子どもが働く環境をなるべく作らないように、大人たちが子どもを見守りながら、そういう仕事を与えないこと。貧しいから子どもも働かないと食べていけないという理屈もありますが、必ずしも食うに困ってやっているわけではないケースも多々あります。そういう状態の子どもをできるだけなくしていくことが大事です。
Iさん:
そうすると、結局、法律とかそういう話になってきますよね。
関谷先生:
そうですね。基本的には法律がしっかりしていれば、それに基づいてこの仕事はやっていい・これはダメとか、子どもにはちゃんと義務教育を受けさせるといったことができるはずなんですが、ご存じの通りアフリカのような貧しい国では、その制度自体がしっかりしていないので、法律で大人と子供をはっきり区別して、子どもには教育を受けさせるということがなかなか難しい状況もあります。また、法律や制度が整っていても、例えば学校からドロップアウトしてしまったり、不登校になったり、いろんな形で学校に行けない子どもたちが行き場を失ってそういう仕事に手を出してしまうといったこともあるわけですよね。だから法律や制度を整えたからといって、必ずしもそれだけでうまくいくわけではない。
どうしたらいいんでしょうね。 難しいですね。
私は、先ほども少し申し上げたように、やっぱり社会がそういうことに関心を持つことということが一番大事なのかなと思います。 正しい答えはすぐに出ないけれども、みんなで一緒に児童労働について考えてみようっていう場を作ること。 それはとっても大事だと思います。日本の若い人で、児童労働のことを知っている人は、そんなにいるわけじゃないと思うので。
あと、日本ではどうなのかというところに、Iさんが興味を持ってくださったこともとても大事で、日本でも、やっぱりそういうことが起きているんですよね。実際に、大変な状況に追いやられている子どもたちがいるわけなので、そういったことも多くの人に知ってもらうべきだと僕は思います。
Iさん:
その、みんなに知ってもらうためのポスターに掲載する内容が、まだあまり定まっていなくて。児童労働の現状を伝えることが目的で、形としては、現地の状態を知っている方のインタビューを掲載したり、今おっしゃっていただいた、児童労働のどんなことが問題で、どういうところが難しいのかといったことを掲載しようと思っています。ただ、児童労働の何が悪いかっていうところが、しっかり定まってないというか、わからないところがあるじゃないですか。なので、それをどういうふうに伝えればいいのかが、難しいなと思っています。
関谷先生:
そこは、難しいですね。ポスターは1枚なんですか?
Iさん:
はい、1枚を考えてます。
関谷先生:
なるほど、まず1枚という限られたスペースに何の情報を盛り込むかっていうのは、私たち研究者の世界でも、一番苦しく悩むところなんです。いろいろ調べると、あれもこれも大事みたいに思うんですけど、そういう時に私だったら、「何を一番伝えたいか?」っていうところから考えると、自ずとポスターの書き方っていうのが定まってくるのかなと思います。そのポスターは誰に見せるんですか?
Iさん:
学校の生徒に向けて見せるんですけど、全体の計画としては、学校でまずこのプロジェクトに協力してくれる人を募って、Teamsを使ってグループチャットを開いているので、そこで意識調査アンケートをしようと今作成中です。 まずは意識調査アンケートとテスト形式の筆記調査アンケートを行なっておいて、作成したポスターを見せた後に、もう一度同じアンケートをとって、どれぐらい理解度が深まるかという比較もやろうと思っているんですけど、そのテスト形式のアンケートを実施するってなったときに、やっぱり明確な答えが出てないとダメだなって思って。
関谷先生:
児童労働に関しては、わからないこともあるけれども、はっきりしていることもあるわけですよね。例えばILOの規定では、軽度な家事労働は認めている。一方で、劣悪な環境の中での労働というのは認めていない。そういった〇×とかで質問を組み立てていくと、案外面白いクイズになるかもしれないですね。 また、Iさんから最初にいただいた相談では、児童労働はやっぱり撲滅しよう!という話だったと思うんですが、僕が知る限りにおいて、それはとても難しいんじゃないかなと思います。 難しい理由はいろんな次元で言えるんですけど、だからこそ、児童労働を全てなくすことはできない? みたいな問いかけをすると、人は色々と反応してきますよね。僕だったらそういうクイズを作るかもしれないですね。
あとは、とっても大変な作業かもしれないけど、レクチャーの中でご紹介した参考書籍の中には、かなり当事者の声が入っています。なので、そういうものも参考にしていただくと、よりリアリティのあるクイズを作ったりできるんじゃないかなぁと想像しています。
→ 続きはこちらからお読みいただけます(PDFダウンロード)
支援ミーティングを終えて
Iさんより:
専門家である教授と直接お話できたことで、日本国内の児童労働について知ることができ、インターネットではなかなか知り得ることができない情報を得ることができました。また、自分の成果物において、本当に良いものなのか自信がなかったのですが、教授に後押ししてもらえたことで自信を持てました。これからもこの経験を生かし、探究に励みます! ありがとうございました。
関谷先生より:
『児童労働』という難しい課題に日本の中学生が独学で取り組む姿に心を打たれました。難しい課題でも、時間をかけて考察していくうちに、いつか解決に繋がる光が見いだせるのではないかと思います。 その考察の過程を大切に、ぜひ頑張ってください。