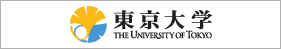東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター(CASEER)では、「初等中等教育における探究学習への支援プロジェクト」において、児童生徒の発意や関心に基づく探究学習に対して専門の研究者が的確なアドバイスをすることにより、探究の成果をいっそう高度で充実したものとすることをねらいに、東京大学の教員もしくは大学院生がオンラインを通じて支援・指導を行っています。
今回は、埼玉県の中学2年生 TさんのSDGsに関する探究プロジェクトを通して出てきた疑問や悩みに、大学院総合文化研究科・附属国際環境学教育機構の前田 章先生がアドバイスしました。
- アドバイスした人:大学院総合文化研究科 附属国際環境学教育機構

前田 章教授
[専門] 環境経済学,資源経済学,ファイナンス,エネルギーシステム,経済理論
[研究テーマ] 気候変動政策の経済モデル分析
→ 前田先生のページへ
Tさんのご相談
企業の経営とSDGsへの対応は、切り離せない不可分なもの
―よりよい議論や理解のベースとなる、ゲームのシナリオ作りとは?
Series2.シミュレーションゲームを通したSDGsの理解促進
Tさん:
私は、埼玉県の中学2年生のTと申します。本日は、学校の探究活動で行っているSDGsに関するシミュレーションゲームについて、先生たちのお力を借りたいと思い、この機会に参加させていただきました。よろしくお願い致します。
前田先生:
よろしくお願いします。私は、専門は経済学なんですが、大学生の時には経済学ではなくて、工学部で電子工学を勉強したんです。元々数学が好きな少年だったんですけれど、色々あって今は、経済学のなかでも特に環境問題であるとか、不動産や都市、エネルギーなどの応用を専門に研究しています。
今日は、まずTさんのほうから、今どんなことを考えているのか話していただけるのがいいかなと思います。
Tさん:
はい、そもそものテーマは「企業」×「SDGs」で、企業が行っているSDGsの取り組みについて知らない人が多いから、その認知度を上げるということを目的にやっていて、その中でも私はESG投資という、企業が行っている投資に着目して、ゲームの中にその要素を取り入れてプレイしてもらうことで、よりみんなの理解が深まるようなものを作れたらと考えています。
前田先生:
そのゲームというのは、どこでどういう形で使おうと思っているんですか?
Tさん:
作成したゲームは、最終的には校内で開かれるワークショップで、生徒にやってもらおうと思っています。
前田先生 :
そのワークショップは、文化祭みたいな感じでやるんですか? それとも何かの大会みたいな感じで?
Tさん:
うちの学校は、土日に授業とは違って、自分たちが好きなことをやれる時間みたいなのがあるんですけれども、その時に生徒が自分たちの行っている活動について説明したりする時間があるので、ワークショップもそこでやる予定です。
資料の方にもう少し詳しい説明があるんですけれども、共有してもいいでしょうか。
Tさん:
今悩んでいるのは、2つめの◆のところに「評価(ESG評価)」というのがあるんですけれども、そこでオーディエンスに対してSGDs対策について発表して、その取り組みがいかに良いものかっていうのを公平に判断してもらおうと思っていたんですけれども、学校の先生と相談していた時に、オーディエンス側がこれだとちょっと飽きちゃうんじゃないかという問題が発生していて、オーディエンス側の人をどう立ち回らせるかっていうのが、難しいところかなって思ってます。
前田先生:
これ、一番初めの、そもそものこのシミュレーションゲームの目的は何でしょうね?
Tさん:
目的は、やはり企業が行うSDGsやESG投資が私たちから見て遠い存在にあるものかなって考えたので、一番身近なゲームという形で実際に体験してもらって、こういうものなんだっていうのを理解してもらうということだと設定しています。
前田先生 :
「売上評価」と「ESG評価」という2つの軸があるんだけど、企業経営を中心にする? それともSDGsを中心にする? あるいはその両方?
Tさん:
基本は企業経営が中心というか、その企業でどういうことができるの? 個人ではなく、もうちょっと大きい存在として、どういうことを行っているんだろう? ということでしょうか。
前田先生:
あと、このゲームをやる人の事前知識については、どのくらいだと想定していますか?
Tさん:
ESG投資については、あまりわかってないという状態。かつ、その企業でどんなことが行えるかについても、あまり理解していないのかなと。
前田先生:
企業経営については、ある程度知っている人を想定しますか? それとも全然?
Tさん :
企業経営についても、あまり知らない人が多いと思うので、ルーレットにするなどして簡略化はしているんですけども、わかってない人の方が多いと思います。
前田先生:
参加者っていうのは、このルーレットを回したり、対策を匿名で発表したりする人のことですよね。それから、それを見ていて、評価して点数をつけるのがオーディエンスですよね。そして勝敗は、参加者サイドは点数が多かったら順位が決まるし、オーディエンスも、自分が応援していたチームの順位が高かったら勝敗が決まるっていう、そういう設定ですよね。
Tさん:
はい、その設定です。
前田先生:
そういう意味では、ゲームの参加の仕方が2通りあるってことですね。わかりました。そのうえで、全体のなかで一番気になるのは、やはり前半の「売上評価」と、後半の「ESG評価」の2つの関連性がないところですかね。 それをもう少し考えたらいいと思うんですよね。
Tさん:
そうですね。その部分の関連性は、やっぱり実際に経営していく上でもかなり重要になると思うので、そこの関わりはちょっと入れたいなって思っています。
支援ミーティングを終えて
Tさんより
今回の支援ミーティングを経て、自分では見つけられなかった新しい視点や気づきを得ることが出来ました。優しく丁寧に教えてくれた先生たちに感謝しております。
先生方にご指摘貰った箇所を意識し作成していきたいと思います。
前田先生より
教育的あるいは学習的要素のあるゲームを作るというのは、試験問題を作るより難しいことだと思います。もちろん試験問題を作るのは試験問題を解くよりも難しい。ですから、Tさんはこれまでやったことのない超絶ハイレベル難易度のことに挑戦しているということになります。その分学ぶことも多いと思います。ご健闘を祈ります。
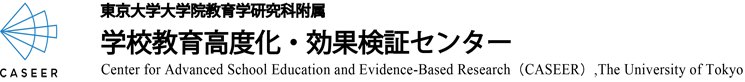


 クリックして拡大(PDF)
クリックして拡大(PDF)